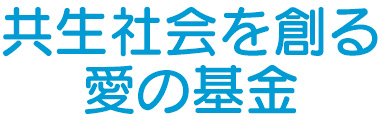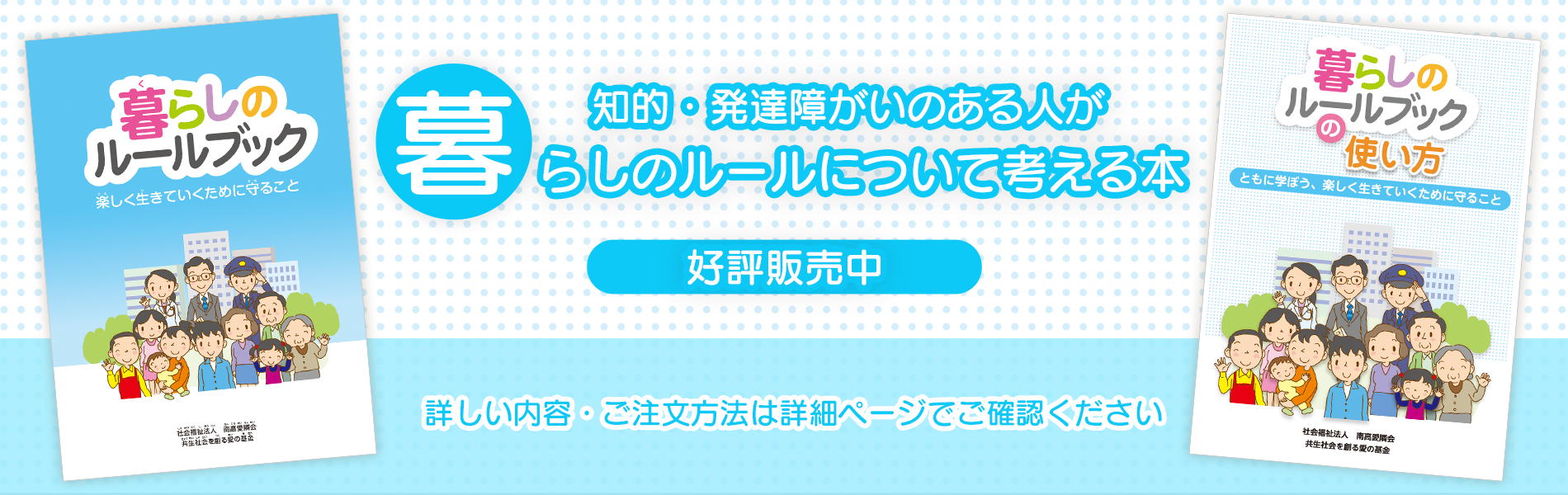浅野史郎さんと村木厚子さんが、愛の基金の生みの親、田島良昭さんについて語ります。
(2021年10月に開催したシンポジウムの第3部です。)
最新のお知らせ
設立趣旨・概要
すべての人が年齢や性別、障がいの有無にかかわりなく、地域でともに暮らし、働いていける「共生社会」を目指し、特に困難な状況に陥りがちな「罪に問われた障がい者」への支援の輪を広げ、支えていく取り組みを行っています。
詳しい内容は「設立趣旨・概要」ページでご確認ください
事業について
共生社会を創る愛の基金では3つの事業を軸に活動を行っております。
- 調査研究事業(本体事業):テーマごとにチームを作って研究事業等に取り組んでいます。
- 助成事業:地域をつないでいく活動に対する助成(地域中核助成)と草の根活動に対する助成(草の根助成)を行っています。
- 広報事業:毎年、シンポジウムを開催する等、広く皆さまにこのような取り組みを知っていただく活動をしています。
詳しい内容は「事業について」のページでご確認ください。
公開中のシンポジウム情報
知的・発達障がいがある人が暮らしのルールについて考える本
知的・発達障がいのある人たちに知っていてほしい、「してはいけないこと(犯罪)」「気をつけたいこと」をイラストでわかりやすくまとめた当事者用テキスト『暮らしのルールブック』と、それを使って行うワークの実施方法をまとめた『「暮らしのルールブック」の使い方』を発売しています。
ぜひ、セットでご活用ください。
詳しい内容と購入については詳細ページでご確認ください。
『暮らしのルールブック』の使い方講座も実施中です。
詳しくは暮らしのルールブック詳細ページをご覧ください。